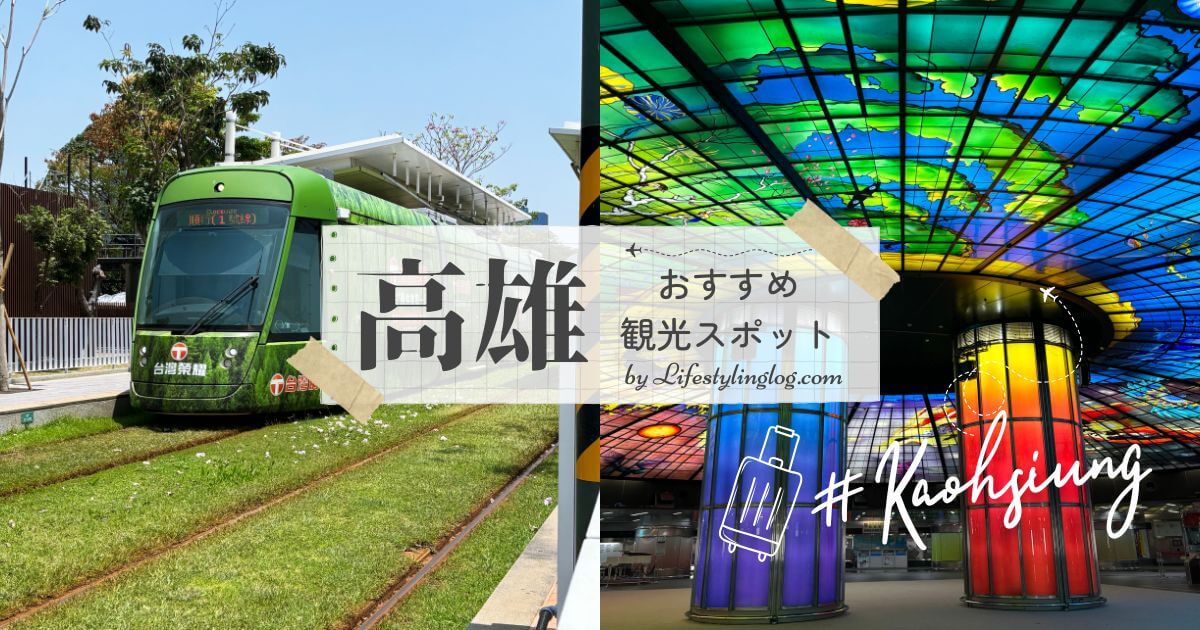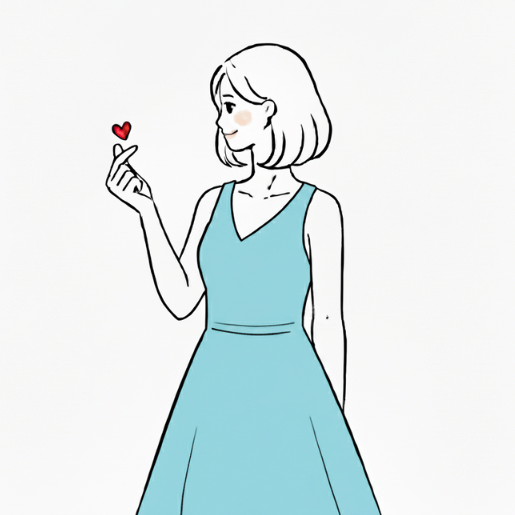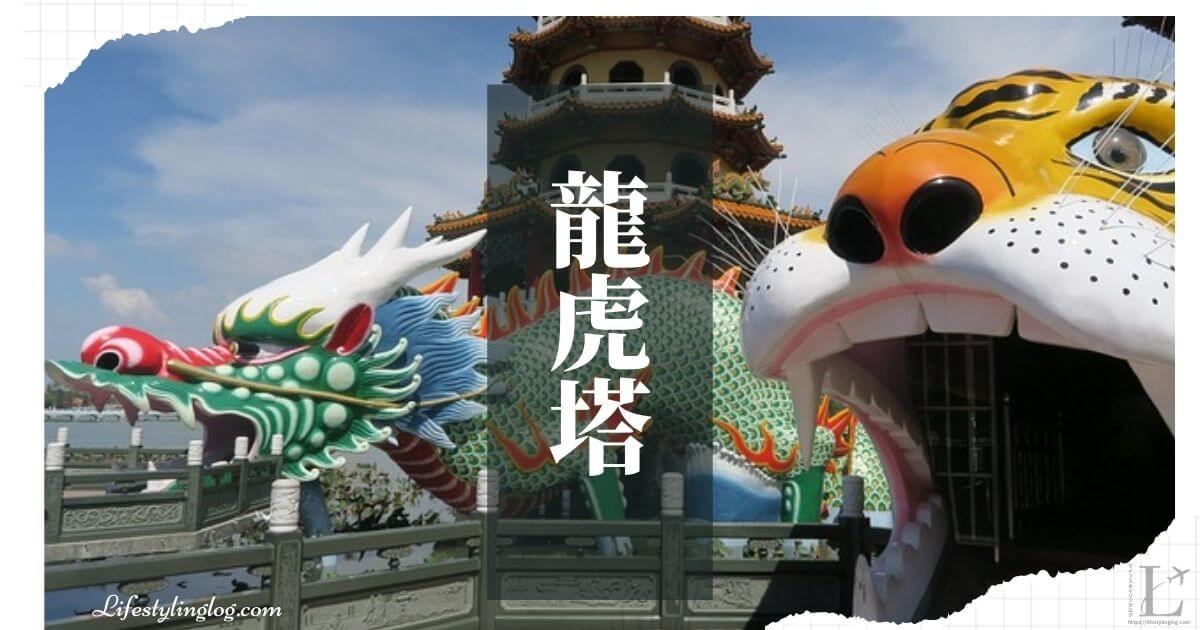高雄の旗津にある旗後砲台。
かつて大砲が設置されていた場所で、その歴史には日本も大きく関係しています。
この記事では旗後砲台の概要と行き方について紹介します。
高雄の旗後砲台
旗後山の山頂に築き上げられた旗後砲台。
中国語表記は旗後砲臺、発音はQíhòu pàotái(チーホウパオタイ)になります。
ちなみに、英語表記はCihou Fort。
旗後砲台からは、旗津の街並みや高雄港など、360度の風景を楽しむことができます。
旗後砲台はなぜ作られた?その歴史と概要
いち観光客として旗後砲台を訪れると、
「旗後砲台からの眺めは絶景!」
…とその景観の良さだけに注目しがちですが、その歴史には日本が深く関わっています。
私自身、何の予備知識もないまま足を運んだのですが、現地で展示物に目を通して、はじめて日本が深く関わっていた事実を知りました。
以下に旗後砲台の歴史と概要について簡単に紹介します。
①牡丹社事件(台湾出兵)
清時代末期、打狗港(現在の高雄港)の治安を守るため、旗後山、稍船頭、大坪頂に砲台が築かれていました。
現存する砲台を築くきっかけとなったのは、1874年の牡丹社事件(台湾出兵)。
この一件により、清朝は沈葆楨を台湾に派遣し防衛面の強化をはかります。
さらに英国人のJohn William Harwoodを雇い、西洋スタイルと中国スタイルの双方の要素を取り入れた砲台を作り、そこに新しい大砲を設置しました。
1875年に建築開始、1876年に完成したものが今も残る旗後砲台になります。
②日本軍の侵攻と爆破
日本が台湾に侵攻した1895年。
日本軍艦の「吉野」が「秋津州」などを率い打狗港を攻撃した際、旗後砲台の一部が破壊されました。
日本統治時代になると、日本軍により大砲が解体され、溶かされてしまったことから大砲は現存していません。
大砲が撤去されると、旗後砲台は廃墟化の一途を辿ります。
③高雄市政府による修復と国定古蹟へ
1985年に旗後砲台が二級古蹟に指定。
1991年、高雄市政府が3年の月日をかけて砲台の修復に取り掛かり、1995年1月1日に一般開放されます。
なお、旗後砲台は2019年に国定古蹟に昇格しています。
3つのエリアで構成される旗後砲台

こちらが旗後砲台の全体図。
旗後砲台は、北・中・南という3つのエリアで構成されています。
- 北エリア:オフィスと兵房
- 中央エリア:指揮区
- 南エリア:砲台と弾薬庫
…という配置になっていて、さらに中庭や祭祀用のエリアもあります。
旗後砲台の見所

赤レンガ造りの正門。
正門にはダブルハピネスを意味する「囍」の文字があり、西洋と中国の折衷で作られた旗後砲台の中国的要素の1つになります。
また、門の上部には「天南」の2文字が見えますが、これは「威震天南」という言葉がベースになったもので、「威震」の部分は日本軍に爆破されてしまいましたが、残った天南の2文字については、古い写真をベースに浮文字として修復されています。

中庭と兵房。

砲台や弾薬庫があるエリア。

防波堤。

旗後砲台の一番高い場所に登ると、絶景を望むことができます。
ただ、まわりに柵がないので、正直かなり怖いです。
私は足が震えて、短い時間しか立っていられなかったです。


こんな感じで旗後砲台からは高雄の風景を楽しむことができます。
ロケーション
旗津フェリーターミナルから、徒歩で約10分〜15分程度でアクセスできます。
アクセス方法は高雄灯台に行く時とほぼ同じで、旗後砲台と高雄灯台の分岐点から左に曲がり、山道を登って行くと旗後砲台に到着します。
山道はゆっくり歩いて5分程度ですが、傾斜がやや急です。
また、暑い時期は直射日光がかなり厳しい場所なので、しっかりと熱中症対策をするようにしてください。